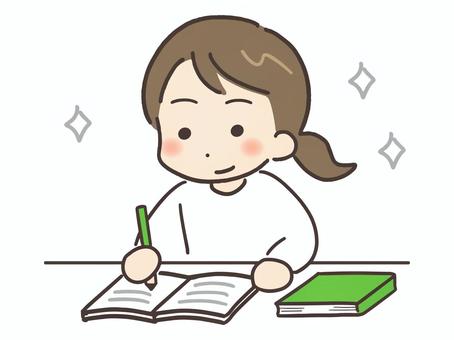こんにちは(^▽^)/リヨです!
今日は、宅建業法の中でも重要ポイントとなる「保証協会」と「8種制限」について復習しました。
📚 今日の勉強内容
✔ 保証協会の弁済業務の流れ
✔ 供託・納付のタイミング
・弁済業務保証金分担金の納付…加入の場合は加入日まで、事務所新設の場合は2週間以内
・弁済業務保証金の供託…1週間以内
・弁済業務保証金不足額の供託…2週間以内
・還付充当金の納付…2週間以内
✔ 8種制限の再確認
①クーリングオフ制度…事務所、営業所、モデルルーム、モデルハウス(専任の宅建士を設置する義務がある場所)クーリングオフできない。テント張りはできる。
クーリングオフができる旨、方法を宅建業者から書面で告げられた日から起算して8日を経過した場合はできない。買主が宅地・建物の引渡しを受け、かつ代金の全額を支払った場合はできない。
②一定の担保責任の特約の制限…引き渡しの時から2年以上の期間となる特約を定めることができる
③損害賠償額の予定等の制限…損害賠償額を予定+違約金は代金の20%まで。超える部分は無効。
④手付の性質、手付の額の制限…代金の20%まで。超える部分は無効
⑤手付金等の保全措置…不要な場合は買主への所有権移転登記がされたとき。未完成物件は手付金等の額が代金の5%以下、かつ1000万円以下。完成物件は手付金等の額が代金の10%、かつ1000万円以下。
⑥他人物売買の制限…取得する契約を締結している(売買予約契約を含む)場合、手付金等の保全措置を講じている・講じる必要がない未完成物件は売買契約を締結してよい
⑦割賦販売契約の解除等の制限…買主が賦払金の支払いを履行しない場合には、30日以上の期間を定めて、支払いを書面で催告し、その期間内に支払がない時でなければ、契約の解除や残りの賦払金の支払請求することができない
⑧所有権留保等の禁止…所有権留保が認められる場合は宅建業者が受け取った金額が代金の額の10分の3以下であるとき
うっかり忘れてしまいそうな細かい項目を重点的に見直しました。
✍ 今日のひとこと
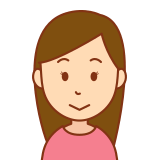
小さな見直しが、大きな自信につながる!
試験までの日数が減ってくると焦りも出ますが、こうして復習を重ねることで、「ここは大丈夫」と言える分野が増えてきました。焦らず一歩ずつ確実に積み上げていきたいです。
📌 明日の予定
明日は「抵当権」をはじめとする「担保物権」の基本について勉強しようと思っています。